カテゴリー:電気主任技術者試験 合格ガイド
2016/01/13
2019/11/20
電気主任技術者試験対策汽力発電の仕組みや特徴は? メリット・デメリットも紹介します!
汽力発電とは聞きなれない名前ですが、水蒸気の力を利用してタービン発電機を回し、電力を得る方法です。火力発電所や原子力発電所では、この方法で電気が作られています。
そこで今回は、汽力発電の特徴や仕組みをご紹介しましょう。汽力発電の歴史は古く、その原理が考え出されたのは2000年以上も前のことです。ですから、それだけ優れた出力システムではありますが、デメリットもあります。
今回は汽力発電のデメリットや、その補い方などもご紹介しましょう。電気主任技術者の資格取得を目指している方も、ぜひこの記事を読んでみてください。
- 汽力発電とは?
- 汽力発電の仕組みは?
- 汽力発電の出力と損失について
- 汽力発電のメリット・デメリットは?
- 汽力発電以外の発電方法は?
2016/01/12
2019/03/14
電気主任技術者試験対策変圧器の原理や構造はどうなっている? 種類とともに紹介!
変圧器とは、電圧を変えるための装置です。海外旅行に行く際に小型の変圧器を持っていったという方もいるでしょう。変圧器は、私たちの生活のいたるところで使われています。
そこで今回は、変圧器の原理と構造についてご説明しましょう。特に、電気主任技術者の資格取得を目指している方は、変圧器についての知識が必須です。一口に変圧器といってもいろいろな種類があります。ですから、知識がこんがらがらないように、系統立てて覚えておきましょう。ぜひこの記事も参考にしてくださいね。
- 変圧器とは?
- 変圧器の構造は?
- 変圧器の種類は?
- 変圧器は意外とデリケート?
2015/12/28
2019/12/23
電気主任技術者試験対策コンバインドサイクル発電の特徴は? わかりやすく解説します!
現在、コンバインドサイクル発電とその画期的な特徴が注目されています。テクノロジーが進化していくのと比例して、電気の供給がますます必要です。また、日本では発電所の安全性も大きな課題でしょう。その点で注目されているのが、コンバインドサイクル発電なのです。
それでは、コンバインドサイクル発電の特徴とメリットやデメリットをご紹介しましょう。
- コンバインドサイクル発電とは?
- コンバインドサイクル発電の特徴
- コンバインドサイクル発電のメリット・デメリット
2015/12/24
2019/12/23
電気主任技術者試験対策火力発電に使われる燃料は? 種類や特徴をわかりやすく解説!
私たちの生活になくてはならない電気、その電気を作っている場所が発電所です。発電所には、原子力・水力・火力などの種類があります。
そこで今回は、火力発電所で使われる燃料の種類についてご紹介しましょう。火力というからには火を起こさなければなりません。では、長時間にわたり火力を維持し続けるにはどのような燃料が最適なのでしょうか?
この記事では、燃料と電気代の関係についてご紹介します。興味がある方は、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。
- 火力発電所の仕組みは?
- 日本の火力発電の方法
- 電気代と燃料の関係
- 火力発電に代わる発電方法はあるの?
- 電力を安定して供給するためには?
2015/12/15
2021/04/07
電気工事士試験対策第一種電気工事士の難易度や合格率はどのくらい? 第二種との違いは?
第一種電気工事士とは、一般住宅や事業用工作物のうち、最大電力500キロワット未満の需要設備の工事ができる資格になります。第二種よりも工事ができる範囲がぐんと増えるのですね。「どうせ取得するならば、二種よりも一種を」と思う方も多いでしょう。しかし、第一種電気工事士は誰でも受験ができますが、免状交付には実務経験が必要になるなど条件があるのです。
そこで今回は、第一種電気工事士の難易度や合格率をご紹介します。第一種電気工事士の資格取得を目指す方は、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。
- 第一種電気工事士と第二種電気工事士の違い
- 第一種電気工事士は筆記試験が難しい?
- 第一種電気工事士の試験対策
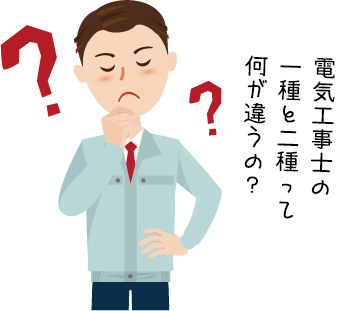
2015/12/14
2021/04/07
電気主任技術者試験対策電験3種の試験はどんな問題が出る?勉強のポイント・コツを解説!
世の中にはいろいろな資格があります。その中でも電気に関するものは需要も高く、取得しておけば就職や転職に役立つでしょう。そんな電気に関する資格の中でも、「電気主任技術者」は人気が高いのです。
そこで今回は、電験3種の勉強法についてご紹介します。電験3種とは、第3種電気主任技術者の略です。いったいどのような問題が出て、どのように勉強すれば合格しやすいのでしょうか?答えは、この記事を読めば分かります。電験3種にチャレンジしたい方は必見です。
- 電気主任技術者とはどんな資格?
- 電気主任技術者の資格を取得する方法
- 電験3種の勉強方法
2015/12/07
2019/03/14
電気主任技術者試験対策電気主任技術者の認定に必要な実務経験は?実務経験を積む方法
電気工事関係の仕事に従事している人なら、電気主任技術者という資格についてご存じだと思います。電気主任技術者になれば、発電所や変電所、工場、ビルなどの受電設備や配線、電気設備の保安監督という仕事に就くことができるのです。電気設備を設けている施設の事業主は、保安の監督者として電気主任技術者を選任する義務があります。つまり、この資格は需要と社会的評価が高いと言えるでしょう。
ただし、試験を受けないで、電気主任技術者として認定されるためには、実務経験が必要です。資格認定のために必要な実務経験にはどのようなものがあるのでしょうか?
「電気主任技術者の資格を取得したい」「資格取得に必要な実務経験について知りたい」「どのような内容が実務経験として認められるのか?」そんな人たちのために、電気主任技術者に必要な実務経験についてまとめてみたいと思います。
- 電気主任技術者の資格について
- 電気主任技術者に必要な実務経験について
- 実務経験として認められる内容について
- 求人における実務経験について
- 実務経験を積める場所や試験について
2015/12/04
2019/03/18
電気主任技術者試験対策仕事の幅を広げたい人必見!電気工事や電気設備に関する資格を一挙紹介
電気関係の仕事をする上で、目指すべき資格があります。電気に関わる資格の需要は高く、転職や就職にも有利になるでしょう。特に、電気工事士や電気主任技術者を目指している人は多いはずです。そもそも、電気工事や電気設備に関する資格にはどのようなものがあるのでしょうか?「電気関係の仕事でもっと上に行きたい」という人は、ぜひチェックしてください。
「電気工事や電気設備に関する資格の種類は?」「資格を取得するにはどうしたらよいのか?」「資格取得のための勉強方法は?」そんな疑問をお持ちの方のために、電気工事や電気設備に関する資格の種類や取得方法・勉強方法についてまとめました。
- 電気工事・電気設備に関する資格の種類
- 資格の取得方法
- 資格取得のための勉強方法
2015/11/30
2019/12/23
電気工事士試験対策電気工事士の受験資格は?電験3種も取得しておいたほうがよい?
世の中に資格はたくさんありますが、電気に関わる資格は需要も高く就職や転職に役立ちます。電気工事士や電験3種の資格取得を目指している方も多いでしょう。
そこで今回は、電気工事士や電験3種の受験資格についてご紹介します。また、どのような方が受験するとよいのかということや、併せて取っておくとよい資格などもご紹介しましょう。電気工事士や電験3種の資格を取得したいと考えている方は、ぜひこの記事を読んで参考にしてくださいね。
- 電気工事士や電験3種とはどんな資格?
- 電気工事士を受験するのに資格は必要?
- 電気工事士の試験について
- 電気関係の資格は実務経験が大切?
- 電気工事士の資格を取得したほうがよい方は?
- 勉強は時間をかけて取り組もう
- 電気工事士に関するよくある質問
2015/11/18
2019/03/18
電気主任技術者試験対策電気主任技術者の選任要件とは?どんなところに必要なの?
電気主任技術者とは、事業用の電気工作物の工事や維持管理・保安を行うための資格です。一定の電圧を使う事業所は電気主任技術者を選任する必要があります。では、いったいどのような場所で選任が必要なのでしょうか?
そこで、今回は電気主任技術者の選任要件についてご説明します。一般家庭以外ならばどのような規模の事業所でも電気技術者の選任が必要なのでしょうか?
また、電気主任技術者の代わりを務められる資格などもご紹介します。電気主任技術者の資格取得を目指している方も、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。
- 電気主任技術者の選任が必要な場所は?
- 電気主任技術者の選任が免除されている施設は?
- 電気主任技術者の選任要件は?
- 電気主任技術者の仕事内容は?
- 電気主任技術者を雇うときの注意点は?
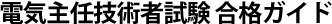
 続きを読む
続きを読む